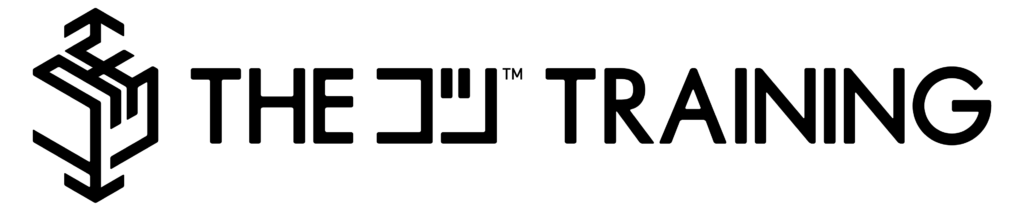ちいさな子どもを抱えているときに、
落とさないようにいつも大事に、大事に抱えてしまっていませんか?
もしかするとそれは、子どもの運動発達を阻害しているかも??
今回は子どもに本来備わった運動能力を引き出し、適切な運動発達を促す抱っこの考え方をご紹介します。
猿のような姿から進化したと言われる我々ヒト
我々がヒトに進化する過程で、猿のように元々樹上生活をしていたと言われていますが、この頃、産まれたばかりの幼い子どもたちは常に大事に抱っこされて育っていたのでしょうか?
想像してみればすぐにわかるかと思いますが、
両手でしっかりと子どもを抱えて木に登ることは不可能ですし、片手で支えながらでも一苦労です。
かといって、抱っこ紐で支えていたはずもありません。
となると、動物園の猿の親子ように親から振り落とされないように子ども自らの力でしがみついていたはず。

今では木に登る必要もなく、抱っこひも、おんぶひもという便利なツールもあるのでそもそもそのような能力は現在子どもに必要でないように思えるかもしれませんが、
『しがみつく』『ぶら下がる』『よじ登る』といった動作は体幹機能を発達させる上で非常に有効な動作なのです。
具体的には、
・脇を締める
・腹筋を利かせる
・股関節(鼠径部)を締める
といった機能です。
これらの能力は、腹圧を適切に高める能力とも深く関わっています。

脳は大きくなり、知能も発達しましたが、筋骨格的な部分はヒトに進化する以前と大きく変わりません。
適切に姿勢を保つ能力、体幹部分をしっかりと機能させて動く能力を身につけるために、このように動物から学べることがたくさんあります。

どのように抱っこ、おんぶすればいい?
子どもが少しでもしがみつくような動きが出来るようになれば、なるべく早い段階でその能力を引き出せるように関わってあげるのがベストです。
「全く支えないようにしよう」と言っているわけではなく、
「しっかりとしがみつくことができているな」、
「落ちそうになっていないな」、
と言うことを親がしっかりと腕の中や背中で感じ、
安全性を確保しながら、必要のない支えを外していくことが重要です。

進化生物学的観点から観てみると『ハイハイ』と同じように『親にしがみつく』のも発達段階で乗り越えるべき課題の1つのように思えます。
抱かれ上手な子(つまり誰でも軽く抱っこできる子)と抱かれ下手な子との違いも、このしがみつく能力の差なのではないでしょうか。
すでに大きくなったお子様には…
鉄棒、うんてい、登り棒、ジャングルジム、木登りなど、
『しがみつく』『ぶら下がる』『よじ登る』
の3つの要素が含まれる遊具、遊び方がおすすめです。

「お腹に力が入っていないなぁ」、「反り腰気味だなぁ」と感じられれば是非このような遊びに取り組んでみてくださいね。
子どもの運動発達を促すにはこちらも参考にしてみてくださいね。